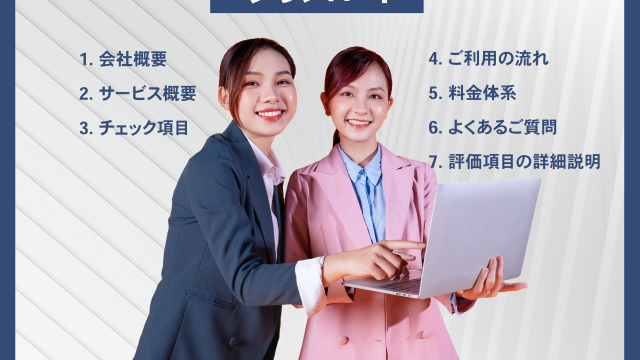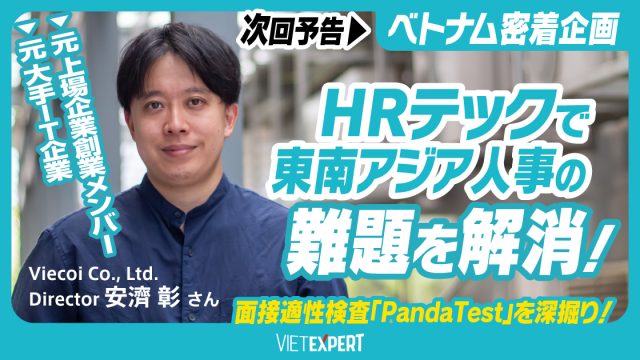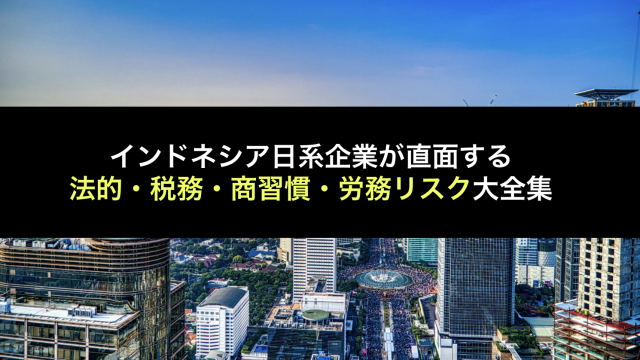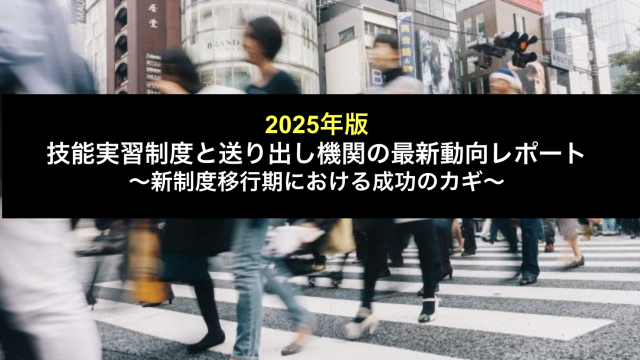屈辱に耐える期間。組織社会化とエンゲージメントの関係
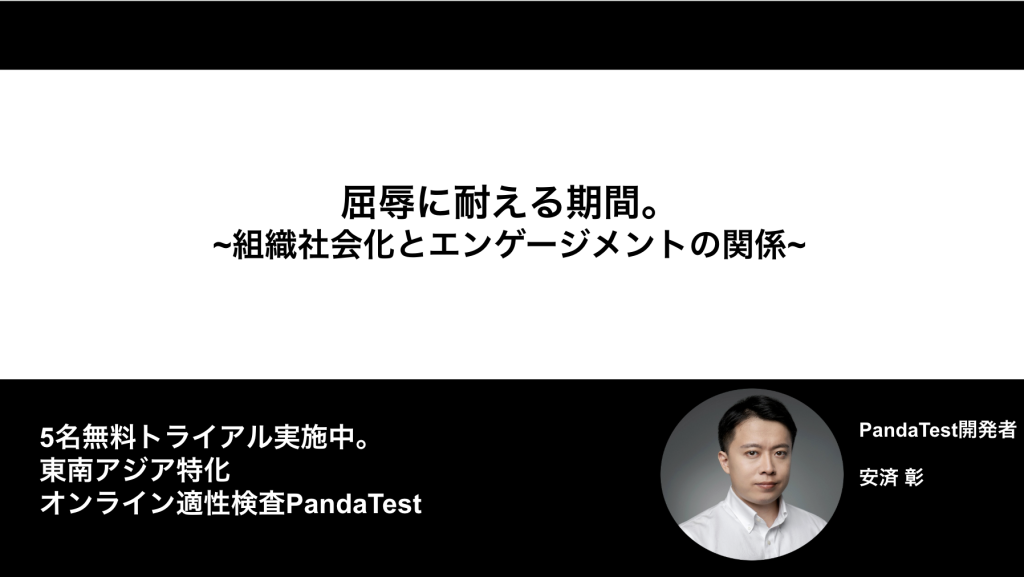
入社してから数ヶ月から1年ほどの間は、「屈辱に耐える期間」と言える。
これは新卒でも転職でも、あるいはプライベートで新しいコミュニティに入るときでも、多くの人が経験する感覚ではないだろうか。
なぜなら、環境が変わると、その組織独自の“アルゴリズム”――仕事の進め方、コミュニケーションの仕方、
評価基準、行動様式など――を学び、受け入れ、適応していくプロセスが必要になるからだ。
どんなに優秀な人でも、最初は自分の力を十分に発揮できず、認められず、時に屈辱的な思いをする。
その過程を経てようやく、その組織の一員として成果を出せるようになる。
組織社会化とは何か
この“耐える期間”を乗り越えられるか、あるいは短縮できるかが、組織の中で活躍できるかどうかを左右する。
心理学ではこれを「組織社会化(Organizational Socialization)」と呼ぶ。
新人が組織の文化やルール、価値観を学び、自らの行動や思考をそれに適応させる過程のことだ。
このプロセスで特に重要なのが「組織内行動特性」である。
これは、組織内で求められる正しい行動様式や、
他者との協働の仕方、責任感やルール意識などを指す。
PandaTestでは、この特性を可視化しており、スコアが高い人ほど早期に組織に馴染み、成果を出しやすい傾向が見られる。
組織社会化とワークエンゲージメントの関係
組織内行動特性が高い人は、早期に成果を出せるだけでなく、自己決定理論に基づくモチベーションの好循環も起こりやすい。
自律的に動ける、仲間から信頼される、成果が認められる――これらが「仕事へのコミットメント度」を高めるワークエンゲージメントへとつながる。
実際、PandaTestのデータでも興味深い傾向が見える。
組織内行動特性が低い人は、ワークエンゲージメントスコアも低いことが多い。
つまり、組織に適応できない人ほど、仕事への熱意や活力も失われやすいということだ。
東南アジアの組織で起こっていること
このサイクル――
「組織内行動特性」→「組織社会化」→「ワークエンゲージメント」→「モチベーション向上」
――が特に重要なのは、
東南アジアの労働市場に特徴的な事情があるからだ。
この地域では、転職の心理的・物理的ハードルが低く、環境に適応する前に「合わない」と感じて職場を変える人が多い。
つまり、「屈辱に耐える期間」を経ずにリセットできてしまう。
結果として、社会化が進まず、長期的な成長や高いエンゲージメントが育ちにくい構造がある。
“屈辱に耐える力”という社会化スキル
たとえば、どれほど高性能なエンジンを積んだ車でも、タイヤが1つ外れていればまっすぐ走ることはできない。
個人の能力(エンジン)を支えるのは、周囲との関係性(タイヤ)である。
自分の力を発揮するためには、
周囲のサポートを得ながら協働するスキル――つまり「発揮率」を高める力――が欠かせない。
この観点で言えば、日本で体育会系人材が重宝される理由の一端も説明できる。
体育会の1年目は、まさに屈辱に耐える社会化期間であり、その中で協働スキルと忍耐力が磨かれている。
候補者を見る新たな視点
今の時代、面接では“スマート”で要領の良い若者が多い。
しかし、真のポテンシャルを見極めるには、「屈辱に耐えた経験」を聞いてみるのが有効だ。
どのような環境で、どのように苦しみ、どうやって乗り越えたのか。
そこには、社会化スキルとエンゲージメントを高める資質が隠れている。
まとめ
「屈辱に耐える期間」は、単なる我慢ではない。
それは、組織社会化のプロセスであり、
自らをアップデートして新しい環境に適応する期間だ。
この過程を意識的に支援することで、個人も組織も、より強く、持続的な成長サイクルを築けるだろう。